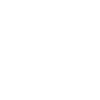BGMを再生する
-
銃弾が来る。魔法が。杭が。剣が。異形の腕が。そのすべてから逃れに逃れ、肉体を半壊に追い込まれながらも、〈ロストメア〉はひた走る。
生まれた理由を果たすために。
手近な家を駆け上がる。大通りは人が多すぎる――薙ぎ払って進むこともできなくはないが、その手間をかけていられる状況ではない。屋根から屋根へと飛び移って門を目指すしかない。
門の近くに大きな建物があった。議会堂。踏み台にするにはちょうどいい。跳躍。壁を蹴り、緩やかな斜面を描く屋根へ跳ぶ。
瞬間、〈メアレス〉どもが湧いた。
右から女――優雅な仕草と裏腹に、携えた銃から残虐の火を放つ。
左から少女――光り輝く糸を操り、魔法を使う構えを見せている。
背後からも少女――可憐さとはほど遠い、重い杭打機を振り回す。
下からは男――飛来する剣をつかみ取り、問答無用で斬りかかる。
上から少年――人ならざる力を身にまとい、同族殺しを厭わない。
〝ここに来る〟。そう看破されていたのだと悟った。門に至る近道。裏返せば、相手にとっては予測しやすい経由地点。こちらを追うというより、ここを目指していたのかもしれない。 -

〈ロストメア〉
(――だが、まだだ!)
-
咆哮。疾走。ただ前へ。そこにだけは敵がいない。追撃のすべてから逃れきりさえすればいい。
銃弾。右腕をひとつもぎ取られる。痛みをこらえ、ゆく。
魔道を練りながら近づく気配。これがいちばん厄介だ。可能な限り距離を取り、ゆく。
強烈無比なる杭の一撃。胸に風穴を穿たれたものの、まだ動く。ゆく。
鮮麗きわまる剣舞の到来。残った右腕を断ち尽くされながらも逃れる。まだだ。ゆく。
黒き拳の猛追。避けられない。蛇腹を串刺しにされる。仕方がない。頭部を分離して、ゆく。
もはや追撃はない。門は目の前だ。残る力を振り絞って飛ぶ。頭だけ。頭だけでも、自由の空へ―― -

リフィル
終わる歴生、果つる黄昏、世はなべて虚ろなる夢のごとく。
-
目の前に、影が立った。
道化の衣装に身を包んだ骨骸の人形が。 -

リフィル
終わりなき夢を見る者よ、現世の理、
確 と知れ! -
骨の骸が、にたりと笑ったような気がした。
逃げることが得意な相手なら、逃げ道を与えてやればいい。
罠の理屈だ。ここしかない――ぎりぎりの状況でそう信じた先にこそ、絶対の牙を置く。
リフィルを魔道士と誤解したのが敵の過ちだった。リフィルに魔法は使えない。使えるのは、骨骸の人形の方だ。
リフィルは、かつて全盛を極めた魔道の家柄に生まれた。
時代が下るにつれ、人の身から魔力が失われ、魔道技術は衰退した。リフィルの家も、古の魔道の術法こそ伝えてはいるものの、もはや誰ひとりそれを操る才を持たない。
その未来を、祖先は予知していた。魔道全盛の時代の当主は、死に際に自分の骸の改造を命じた。その身に蓄えられた膨大な魔道技術を活かす、骸型の魔道書として。
そのため、魔法が失われた時代においても、一族の者が正しい手順を踏みさえすれば、骸を操り、失われた魔法を行使することが可能だった。
リフィルの一族は、代々この骨骸を操る〝道具〟を輩出し、魔道の存在を世界に〝保存〟することを至上の目的と定めた。リフィルとは〝代替物 〟――年を経て〝道具〟が使い物にならなくなるたびに、次代に継承され続けてきた呼び名に過ぎない。
だから、リフィルに夢はない。魔道を世界に残し続ける。そのためだけに生まれ、育てられた身だ。他の夢を見ることなど許されなかったし、そのつもりもない。
そんな彼女にとって、この都市の存在は都合が良かった。〈メアレス〉として〈ロストメア〉と戦っていれば、魔道の現存を示し続けることができるし、魔法の源たる魔力を手に入れ続けることもできる。
自分は生涯、こうして生きていくのだろう。この身が老いて、次代の〝代替物 〟が現れるまで。 -

リフィル
(夢は見ない)
-
見たことすらない。
-

リフィル
(目の前の敵を倒す――ただそれだけでいい)
-
だから、この好機を逃すつもりはない。
糸を操る。呪文を唱え、骨骸に命令を打ち込む。骸が応え、骨の指先で印を結ぶ。空中で茫然となっている〈ロストメア〉の目の前に、巨大な魔法陣を描き上げる。 -

リフィル
〈見果てぬ夢〉なら――らしく潰れろッ!
-
膨大なる雷の奔流が、〈ロストメア〉の頭部を消し炭に変えた。