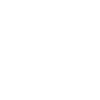-

シューラ
(みんなのために。モニスさんは、その命を使った)
-
見返りも称賛もなく、ただ孤独に戦った。
-

シューラ
(私たち〈號食み〉こそ、そうでなきゃいけない)
-
世界を巡り、祝福を授ける。禁具を見つけ、封印を施す。
ふたつの使命は、同じ理屈でつながっている。
まるで異なる文化を持った氏族が息づく世界。あまりにもいろんなことが違いすぎて、すぐばらばらに砕けてしまいかねない、脆く儚くいびつな世界。
〈號食み〉は楔 だ。この世界が砕けてしまわぬよう、破片と破片を繋ぎ合わせる。あらゆる氏族を訪ね歩いて祝福し、同時に世界を脅かす禁具を封じてゆくことで。
世界のために。大地に生きる者たちのために。自らの命、存在そのものを賭すことこそ、〈號食み〉の使命なのだ。
生半可な覚悟でできることだとは思っていない。多くの〈號食み〉が、禁具を封印するために命を落としてきた。シューラとて、今まさに生と死の境にいる。 -

シューラ
(無傷じゃ切り抜けられない)
-
わかっている。それでもやるしかない。それが、自分の選んだ道であり、誇りなのだ。
同じ道を、モニスも選んだ。全身全霊を費やし、なすべきことをなして、息絶えた。彼と同じ苦しみを味わいながら進むからこその敬意が、シューラの背中を押していた。 -

シューラ
く、うっ……。
-
足が震え始める。悪魔に肺を握り潰されるような痛みと息苦しさが襲う。思考がちぎれ、意識が徐々に濁っていく。苦しみから逃げ出したいという気持ちと、死への恐怖が止めようもなく膨れ上がっていく。
-

シューラ
(逃げるな! これは……モニスさんの遺してくれた道だ!)
-
心で叫び、怯える自分を叱咤した。
誰もいない雪原――身を切る寒さ――轟音のなす静寂――痛みばかりが満ちる吹雪の中で、誰に知られることもなく命を使った男が、拓いてくれた道なのだ。自分の痛みなど、モニスの感じたそれに比べれば、たかが知れている。
守られている 。フレーグが、後をつけるレイルのため、雪をかきわけ道を築いたように。死んだモニスの遺した道に、守られている。それなのに、弱音を吐けるわけがない。 -

シューラ
ぐ――う――。
-
膝が落ちた。やわらかな雪のベッドに倒れかかる身体を、辛うじて杖で支える。
-

シューラ
(嫌だ――)
-
じんわりと、瞳に涙がにじむ。辛さと悔しさ。これだけ守られていながら、使命を果たすこともできないなんて。モニスの願いを無にしてしまうなんて。それは。それだけは。絶対に、嫌だ――
-

レイル
負けないでッ!!
-
烈しい叫びに耳を撃たれて、シューラはハッと顔を上げた。
振り向くような余裕はない。ただ、叫びが。叫びだけが。叩くように、背を押した。 -

レイル
あたしが――守るから! だから、負けないで!
-
叫びが、あたたかな力に変わるのを感じる。やわらかな守護の力。フレーグにもらったものに重なって、もうひとつ――雛鳥を守ろうと広がる、優しい翼のように。
-

レイル
だから――お願い!
-
もはや号泣と言っていい涙混じりの雄叫びが、熱く背筋を焼き焦がす。
-

レイル
負けないって、誓ってッ!!
-

シューラ
――うん。
-
進む。前に。
頬を伝う涙の熱さが教えてくれる――まだ自分の中の熱が尽きていないことを。
死ぬなら、それを絞り出しきったあとだ。 -

シューラ
負けないよ――私――絶対に……!
-
目の前に広がる雪原が、淡く笑っているようだった。意地を張らず、諦めればいい。そうすれば、この苦しみを終わらせることができると――楽になれると、
謳 っている。
それを無視して、シューラは進む。
巡る血潮が、吼えている。今まで巡った各地の名産――己の血肉となったそれらには、多くの氏族の、無数の願いが染みている。それが、シューラに力をくれる。純然たる力。生きて、前に進むための力を。
剣が近づく。どんなものでも無遠慮に、委細構わず喰い散らかすだけの、暴食の刃。シューラは、むっと眉をひそめて剣を見る。 -

シューラ
食べるって、そういうことじゃないよ。
-
言って、踏ん張る。杖にしていた槍を掲げ、軽く撫でると、槍が待ってましたとばかりに大口を開いた。
限界だ。前が見えない。赤だか白だか黒だか、もうまるでわからないようなぐちゃぐちゃの色合いで視界が埋め尽くされていく。あ、これ、やばいかも――と思ったときには、もう、身体が傾ぐのを止められなかった。
手を伸ばす。ぎりぎりまで。たとえ倒れようとも喰らいついてやる――そんな気持ちで。〈號食み〉ゆえに極めて正確に感じ取れる、魔剣のあるはずの位置へ、精いっぱいに槍を伸ばす。 -

シューラ
く――うぅぅううううっ……あぁああぁああっ!!
-
手応えがあったかどうかも、わからないまま。
わずかに残った力を出し切り、シューラはその場に倒れ込んだ。