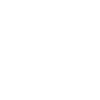-

シューラ
正直なめててすいませんでしたぁーっ!
-
そんなシューラの謝罪など、吹雪の中では、まさに文字通りどこ吹く風だった。
視界は果てしなく真っ白に染め上げられ、唸る轟音と容赦のない冷気で、耳が耳当てごと食いちぎられそうなほどに痛い。降り積もる雪は、重たい泥沼のように足を絡め取り、とても歩けたものではなかった。
竜のフレーグが、「危険」と言うレベルである。人間にとっては、そもそも出歩くこと自体が無謀な環境だった。
シューラにできることは、フレーグの背にしがみつき、道を示すことだけだった。フレーグの歩みは、いつも通りゆったりとしたものだったが、雪に阻まれて足を止めることもなく、着実に前へ進んでいく。それだけでなく、両の翼をかざして背のシューラを守る楯にしてくれているし、何より鱗を通して伝わってくる体温の高さが、この吹雪の中ではありがたい。あらかじめ日光を浴びておくことで、その熱を取り込み、さらに魔力で長時間維持させることができるのだという。これは、人間にはできない芸当だ。 -

シューラ
あ、フレーグさん、もうちょっと右。
-

フレーグ
承知しました。それにしても、禁具のありかなど、この吹雪の中でわかるものなのですな。
-

シューラ
禁具の気配っていうか、においっていうか。五感とは違うところで感じてるんだよね。
-
祝福を授けること以外に、禁具を封じることもまた、〈號食み〉の大事な役目である。
魔法によって特殊な力を持たせた道具を、呪具と呼ぶ。中でも、極めて強力かつ極めて倫理的に問題のある魔法――禁術を付与された呪具を、禁具と呼ぶ。ものによっては触れることさえ危険なそれらを、〈號食み〉は身に宿すトーテムの力で封じることができるのだ。
また、禁具の存在を感知する、特殊な感覚を備えてもいる。 -

シューラ
あんまり距離があると、わかんないんだけどね。村の中じゃぜんぜんだったけど、今は、はっきり感じる。
-
やまない吹雪、というのが気になった。単なる異常気象ではなく、何らかの禁術や禁具のせいで起こっているものだとしたら――そんな、できれば当たってほしくない推測が当たってしまった結果だった。
-

シューラ
ちゃんと近づいてるから、もうちょっとしたら辿り着けるはずだよ。
-

フレーグ
私は平気ですが、シューラさまはいかがですか?
-

シューラ
ありがとう、だいじょうぶ。ただ、口の中に雪ばっか入ってきちゃって……雪も雪で味わい深いんだけど、さすがにおんなじ味が続くと、飽きちゃうんだよね。
-

フレーグ
我が家の特製果実ソースでも持って来ればよかったですかな。レイルも喜びますし。
-

シューラ
あ、それは味わってみたいなー。
-
言ってから、シューラは、「ん?」と首をかしげた。
-

シューラ
フレーグさん?
-

フレーグ
なんでしょう。
-

シューラ
今の、なんか、レイルちゃんがここにいるみたいな言い方だったけど。
-

フレーグ
いますよ。
-

シューラ
いるの!?
-

フレーグ
ええ。村からずっとついてきております。
-

シューラ
それ、だいじょうぶなの?
-

フレーグ
私の後をついてくるくらいなら、なんとかなるでしょう。あの子も竜人ですからね。
-
フレーグの口調は、あくまでも、のほほんとしたものだった。
-

シューラ
すごいね。獅子は子を千尋の谷に落とす、みたいな。
-

フレーグ
おや、我が氏族の風習をよくご存じで。
-

シューラ
やるの!?
-

フレーグ
大人になってからでは、意味がありませんからな。翼が生えますので。
-

シューラ
でも、怪我しちゃわない?
-

フレーグ
しますよ。ですが、死にゃしませんので。
-

シューラ
大変だなぁ……
-
シューラは、しみじみとうなずいた。
人間の感覚で言うと、ちょっと虐待なんじゃないかと思ってしまったりもするが、強靭な肉体を持つ竜や竜人たちにとっては、〝転んだ我が子が自力で立ち上がれるよう見守る〟くらいの感覚なのかもしれない。
この世界には、いろんなトーテムがある。その数だけいろんな氏族がいて、それぞれいろんな考え方や風習がある。「なにそれ!?」と思うことも多々あるが、それを認め、受け入れ、祝福を授けることが〈號食み〉の役割だ。
そして、〈號食み〉として各氏族を回ってきたからこそ知っている。たとえ生き方も価値観も、見た目も能力も何もかも違う氏族であろうと、共通点が見つかることもあるのだと。
たとえば――親が子を、子が親を思う気持ちは、多くの部族にとって、重く、強く、尊いものだ。 -

シューラ
私たちが、モニスさんを捜しに行こうとしてるって、そう思ったのかな。
-

フレーグ
あれは、もっと聡く、もっと強い子ですよ、シューラさま。
-
フレーグは、鷹揚に笑った。
-

フレーグ
〈山の守り〉が弱まった原因を突き止める。父が果たせなかったことを、自分が果たす。そのために、あの子はついてきているのです。
-
揺るぎない誇りに満ちた微笑みだった。