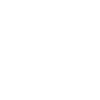-

シューラ
これって……。
-
辿り着いた先にあるものを見て、シューラは思わず息を呑んだ。
悪意と憎悪を塗り固めて鍛えたような、黒く禍々しい一振りの剣。それが雪原に突き立ち、純白の世界を穢している。
そのさまが見えたのは、剣の周辺――この辺り一帯だけが、まるで台風の目のように吹雪から取り残されているからだった。
耳を潰す轟音も遠く、目を叩く豪雪もない、静寂の世界。
だが、シューラを驚かせたのは、黒い剣でも、静けさでもなかった。
微動だにせず、黒い刃の傍らに座る、ひとりの男性。
からからにひからびた皮膚が骨に張りつき、その上から冷たい霜の死に化粧を施されている。
人の身を捨て、この純白の世界とひとつになった聖者のような――どこか厳かでありながら、ぞっとするほど物悲しい光景だった。 -

レイル
パパ――
-
透明な声が、背後から聞こえた。
足音。レイルが、雪を踏んで歩み出てくる。大きな瞳が茫然と見開かれていた――もの言わぬ男の姿を、少しでもその瞳に映し出そうとしているように。 -

フレーグ
結界ですね。
-
フレーグが言った。あらゆる感情を置き去りにして、理性で塗り固めた大人の声だった。
-

フレーグ
清らかなる守護こそ、〈白霊竜の金色の翼〉に授けられた力。この剣の周辺に、邪気を抑え込む結界が張られています。
-

シューラ
あの剣……命を、吸い上げるんだ。
-
黒い刃から発される魔力を読み取り、シューラは告げた。あまりの禍々しさに、直視しただけで激しい頭痛を覚えたが、無理に振り払って言葉を続ける。
-

シューラ
山や、森や、大地や、生き物や――あらゆる生命に宿る精気を、根こそぎ吸い上げていく。そういう禁具だと思う。あの吹雪は、精気を奪われた自然が、痛くて暴れてるせいなんだ。
-
目を伏せた。胸にこみ上げてくるものを抑え、舌を動かす。状況を
咀嚼 し、真実へと辿り着くために。 -

シューラ
剣の力を、結界が抑え込んでる。だから、こんなものですんでるの。本当だったら、もうとっくに山が枯れてたっておかしくない。あれは……そのくらい凶悪な品だから。
-

フレーグ
つまり、モニスが――
-

シューラ
吹雪の中で、これを見つけた。それから、これ以上被害が広がらないように、結界を張った。剣の周囲に。自
分 の 精 気 を 吸 い 尽 く さ れ な が ら 。 -
どれほどの覚悟を要することだっただろう。
あれほどの吹雪のなか、魔剣に命を吸い取られながら、死後も残るほど強固な結界を張るというのは――どれほどの覚悟が、意志が、必要とされたことだっただろう。
あるいは、己の命も魂も、この結界に込めたのかもしれない。剣に精気を吸われたことが死因ではなく――そうなる前に己のすべてを費やしたからこそ、これほど強力な結界を築けたのかもしれない。
〝ここで止めなければならない〟。そんな意志を、ひしひしと感じた。今、ここで、俺が止めなければならない――たとえ一時しのぎだとしても。そうしなければ、山に眠る竜たちが、剣の力に喰われてしまう。あるいは、放っておけば、いずれ里までも蝕まれ――
自分の娘が、死んでしまう。
だから、命を懸けたのだ。後に続く者がいることを信じて。散る覚悟で、力を使った。
命の結界。自分以外の、何もかもを守るための。 -

シューラ
…………
-
シューラは、フレーグの背を降りて雪原に立った。
背にくくりつけていた槍を手にして、剣の方へ歩みを進める。
とたん、くらりとめまいに襲われた。「く――」呻きを嚙み殺し、足を動かす。ざく、と雪を踏み割っているはずが、まるで雲を踏んでいるような、ふわふわした心地しかしなかった。 -

フレーグ
シューラさま!
-

シューラ
あの剣を、封印する……
-
一歩。鉛を流し込まれたように重たい足を、どうにか持ち上げ、前へ。
この結界は、あくまでも、周囲への影響を抑え込むためのものだ。結界の中に入り、剣に近づけば、精気を喰われることになる。 -

シューラ
〈號食み〉の、使命だから……
-
一歩。ぐらりとよろけ、思わず槍を杖にした。目と口のついた〝顔あり〟の槍が、じろりと睨んでくる。
-

フレーグ
であれば、これを――
-
フレーグが、ふうっと息を吐いた。魔力そのものたる竜の吐息に包まれ、全身にのしかかる重さがわずかに和らぐのを感じる。これもまた、〈霊翼族〉の守護の力だろう。
一歩。雪に足を取られそうになりながら、さらに進む。冷気の刃が、分厚い防寒着さえ貫いて、骨の髄まで斬りつけてくるようだった。シューラは歯を食いしばった。モニスは吹雪の中であの剣に近づいたのだ、という思いが、弱音を吐くことを許さなかった。
歩くにつれ、強まっていくものがある。恐怖より、悲しみよりも強く、胸を満たす感情。
敬意。
ひとりで散った、モニスへの。