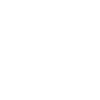-
ジースは、力なく、自らの身体をまさぐった。
本当は、何もせず突っ伏してしまいたかった。もう、何も考えたくない。この雨のなか、地面に倒れ、気が済むまで泣き尽してしまいたかった。
しかし、そうしたところで、きっと今後一生、気がまぎれることさえないだろう。誰もいない村でただひとり、妻を狂わせ村を滅ぼした罪に震えながら過ごすなど、とても耐えられるものではなかった。
懐に、覚えのないものが入っていた。鈍い輝きを放つ宝珠。見たことさえないそれが、きっと、〝すべてを忘れさせる〟禁具なのだろう。
すがるように宝珠を握り込む。 -

ファルク
だめですよ。
-
白い一閃が、正確に宝珠だけを跳ね飛ばした。
月明かりを照り返し、くるくるときらめきながら落ちる宝珠を手の中に納めたファルクが、じろりとジースを睨んだ。 -

ファルク
これはもう使わせません。
-

ジース
忘れさせてくれ……
-
ジースは泣いた。雨の中で。どれが自分の涙なのか、わかりさえしなかった。
-

ジース
頼む。何もかも、忘れさせてくれ……ここであったことも――俺が俺であることも――生きていることも――存在していることすら――ぜんぶ、忘れさせてくれ……こんな、こんな形で生きていたくなんかない!
-

イルーシャ
ジースさん。
-
イルーシャが、そっとかぶりを振った。静かな挙措だが、彼女の瞳には、有無を言わせぬ強さがあった。
-

イルーシャ
この村で、あなただけが生きていたのは、あなたの娘さんが、必死に奥さんの目を逸らしていたからですのよ。
-

ファルク
あんたを守るのが限界だったみたいですけどね。それでも、ずっと助けを呼んでたんです。俺らは、その声を聞いてきたんですよ。
-

イルーシャ
娘さんは、亡くなられてからも、あなたがたをずっと見ていたのですわ。奥さんが悲しみのあまり倒れられたことも、あなたが禁具を使おうとしたことも、すべて見ていて――そして、あなたを守るために、魂を尽くしたのです。
-

ファルク
あんたがどうなろうが、俺はどうだっていいんですけどね。あんたを思う娘さんの気持ちは無下にはできねーんです。
-
生きている人間の願いより、死んでいる人間の願いを優先するのか――ジースはそう叫びそうになったが、寸前で口をつぐんだ。大切な娘が、こんな自分を思って願ったことだと思うと、何も言えるはずがなかった。
ジースは、がくりとうなだれ、途切れ途切れに嗚咽をこぼした。
これからどうすればいいのか――覚えてもいない罪と、どう向き合っていけばいいのか――まるでわからないまま、抑えきれない感情をこぼし続けた。
イルーシャとファルクは、慰めるでもなくきびすを返し、広場の方へと向かっていった。
-

ファルク
安易な道を選ぶから、こうなるんだ。
-
ジースの嗚咽を背中で聞きながら、ファルクは毒づく。
-

ファルク
死者が死を受け入れてるのに、生者が未練たらしく引っ張ろうとするなんて、まったく迷惑な話だ。
-

イルーシャ
それだけ愛が深かったということよ、ファルク。
-

ファルク
愛してるんなら、安らかに眠らせてやれってんだ。要するに、自分が悲しみに耐えられなかったってだけでしょ。
-
にべもなく言って、ファルクは鼻を鳴らす。
人の魂は、死後、死界に赴き、次なる命に生まれ変わる。死とは、その間に訪れる、一時の安らぎであるべきなのだ。人生というものが、苦痛と喜びに満ちたものであるからこそ、死は無上の休息にして、無窮の静寂でなければならない。それが〈死焔族〉の考え方だ。
世界を旅し、死者を鎮めているのも、生きとし生けるもののためではない。死者が正しく黄泉路に逝けるように――死後の安らぎを得られるようにだ。
〝池〟に、大量の魂が渦巻いているのが見える。ジースの妻に喰われ、自分が自分であることすら忘れさせられていた魂たちが、ようやく痛みと嘆きを思い出し、おうおうと泣いていた。放っておけば怨念となってしまうかもしれない。
誰にも顧みられぬ者たち。救いも得られず、苦しみながらさまようことしかできない者たち。
そんな魂を鎮め、慰め、導き、弔ってやることが、〈死焔族〉の使命なのだ。 -

イルーシャ
導いて差し上げますわ。
-

ファルク
おとなしくしてくださいよ。
-
告げて、ふたりは手を伸ばす。
彼らが迷わずにいられるように。もう泣かなくていいように。
すべての苦しみから解き放たれ、希望を胸に、また生まれることができるように。