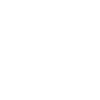-
まるで、家という家が血を吐いているようだった。
深い夜陰に包まれた村――そのすべての家から、先ほど見たのと同じ赤黒い肉塊が、うぞうぞと這い出してくる。まるで、巣に水を流し込まれた虫たちが、あわてて飛び出すように。
外に出たファルクは、そんな光景を鎌で指し示した。 -

ファルク
あれが、村人ですよ。あんなのと仲良く話をしてたって言うんですか?
-

ジース
そんな……そんな――
-
ジースは後ずさり、首を横に振った。目に映る光景が信じられない――こんなものは、見たこともない。
村。確かに、彼の生まれ、生きてきた村だった。輪郭だけは。
みなの住んでいた家、みなの暮らしていた道はそのままに、人の気配がまるごと消え失せ、代わりにおぞましい肉塊が地を這っている。大人たちの陽気な声、子供たちの活発な笑い声はなく、ざあざあ叩きつける雨音と、金属をこすり合わせたような不気味な叫びだけが、陰々とこだまし続ける。憩いの場であった広場は陥没し、そこに雨水がたまって、ほとんど池のようになっている―― -

ジース
なんだ、これは……こんなの……こんなの、俺は知らない! 知らないぞ!
-

ファルク
毎日、そう言ってんでしょうね、あんた。
-
鎌を手に、ファルクが前に出た。
-

ファルク
外に出るたび、あれを見て、そう言って家に戻る。それで、けろっと忘れるわけです。この村がどうなってるのか――誰がこの村をこんなにしたのかさえも。
-

ジース
俺が――俺がやったっていうのか? 馬鹿な! 俺は何も知らないのに!
-

ファルク
だから、忘れてるだけだって、何度言わせんです。
-

イルーシャ
そういうのは後になさい、ファルク。
-
イルーシャが、すっと目を細めた。瞳から春のようなあたたかみが消え去り、代わりに透徹した戦意が宿る。
-

イルーシャ
今は、あの方々を弔って差し上げるのが先よ。
-
村中から這い寄ってきていた肉塊が、一斉に裂けた。
あちこちで巻き起こる血の噴水――そのなかから、ぞろりと現れるものがある。
妻の首。無数。蝶がさなぎを脱ぎ捨てるように、肉塊から顔を出し、こちらを見つめる。蛭めいた蛇腹を伸ばし、首を高く高く持ち上げて。
悪夢だった。そうとしか思えなかった。一度見れば、生涯忘れることもないほどの――そんなものを、俺は忘れていたというのか? -

ファルク
みんな、喰われてるみてーだな、姉ちゃん。
-

イルーシャ
喰われて、忘れさせられているのね。自分が誰だったのか。何もかも忘れて、分身を詰め込むための入れ物にされている。
-

ファルク
それでも魂が消えたわけじゃない。
-

イルーシャ
ええ。忘れているだけ。解放し、死界へ導いて差し上げることはできるわ。
-

ファルク
なら、やるしかねーな。
-
言って、ファルクは疾走を開始した。
速い。まさしく疾風迅雷の速度で、怪物の群れに飛び込んでいく。
妻の顔が五つ、かっと大きく口を開いた。耳まで裂けた口のなかに、のこぎりも色を失いそうなほど鋭い牙が並んでいる。殺意に満ちた咆哮が、ごうごうと重なった。 -

ファルク
ライズ――〈凶騒の支配者〉!
-
ファルクの鎌が、符を喰らう。次の瞬間、怪物たちの咆哮さえ圧倒する騒音を伴って、鮮やかな一閃が夜を裂いた。斬り断たれた顔がぼとぼとと落ちる音を背に、ファルクはさらに前へと駆け込んでいく。
少年の脇腹や首筋を狙い、怪物たちが横合いから跳びかかる。それを見たイルーシャが、無言のまま立て続けに引き金を引いた。月明かりだけが照らす夜、ろくに狙いをつけたとも思えない速度で、次々と怪物の頭部を狙い撃っていく。
何体かが反転し、イルーシャの方へ向かった。イルーシャは銃を下げ、代わりに大筒を構える。ひょいと口に符を放り込むと、大筒がつつましやかにそれを喰らった。 -

イルーシャ
〈破邪双銃〉!
-
大筒に魔力があふれ、荒れ狂う。それをどうどうとなだめるようにしながら、迫りくる怪物の群れへ向け、引き金を引いた。
-

イルーシャ
〝フルフレア〟!
-
どん、と腹に響く音が、いくつも響いた。大筒が何発もの魔力の砲弾を吐き出した音だ。怪物たちは、一体や二体が撃たれようとも、残る面々で嚙み喰らえば問題ないと考えていたのかもしれないが、それは甘い目論見だった――命中した砲弾は轟音とともに爆炎を撒き散らし、そばにいた別の怪物をも巻き込んで、一緒くたに焼き尽くしていった。
ファルクの方も、踊るような足さばきで敵陣を駆け抜け、続々と首級を挙げている。
悪夢的な見た目にも臆さず、圧倒的な数にも怯まず、淡々と冷徹に敵を仕留めていく。そんなふたりの方こそ、よほど冥府の死神めいていた。 -

ファルク
本体はどこだ? そろそろ、出てきてくれてもいい頃だけど――
-
ごぼり、と。
広場だった場所を占める池に、それ全体を揺るがすほどの泡が弾けた。
ごぼり――ごぼり――池の水面が間断なく、激しく泡立ち始めている。
池が沸騰したようだった。怒りのあまり――怨みのあまり。ぼこぼこと無数の泡を噴き、何かを訴えかけている。
やがて、水面がゆっくりと盛り上がった。
何かが。池全体を埋め尽くすほどの巨大な何かが、水面を割って現れようとしている。
何か――などと言うまでもないことに、ジースはとっくに気づいていた。
気づいていたが、認めたくなかった。何も見なかったことにしたかった。あんなもの――あんなおぞましいもので、唯一の宝を、大事な記憶を穢されたくなくて、ぶんぶん首を横に振り、子供のように泣き喚いた。 -

ジース
し――知らない……
-
言葉だけが、滑るように口から洩れる。
-

ジース
俺は――俺は――こんなの、知らないぃいいっ……!
-
目線の先に、妻がいた。
池からせり上がる、大きな大きな妻の頭。目を逸らしようもない――どうしたって視界に入ってくる。
だが、目が合うことは決してなかった。
両目は、虚ろな洞 となっていた。いかなる光にきらめくこともなく、いかなるものをも映すことのない虚無的な闇だけが、寂しくわだかまっていた。
眼窩にたまった池の水が、ざばりと、滝のように流れ落ちた。