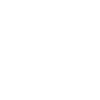喰牙RIZE2 -Tearing Eyes- サイドストーリー
「イルーシャ&ファルク篇」
-
どん、どん、という音が、騒がしい雨音を突き破って響いた。
-

ジース
おや……誰かな。
-
ジースは立ち上がり、家の玄関口へと向かう。
こぢんまりとした木造の家は、容赦を知らない長雨に屋根を叩かれ続けたせいで、すっかり疲れ果てて見えた。あちこちに雨漏りがあって、ぴちゃん、ぴちゃん、と、まるでしくしく泣くような物悲しい音を立てている。
それでも、ジースにとっては思い出深い我が家である。優しく気立てのいい妻、明るく元気な幼い娘、飯のありかを探す猫――大事な者たちと過ごした、大切な家だ。その思い出だけが、ジースの唯一の宝だった。
少し、警戒しながら扉を開く。暖炉の灯りが外に漏れ、溜め込んだ小便のような勢いで降り注ぐ雨粒を――村で冗談交じりに使われる言い回しだ――おぼろに照らした。 -

イルーシャ
……もし。
-
扉の向こうの闇に、突然、ぼうっと白いおもてが浮かんだ。
-

ジース
ひっ。
-
思わず息を呑んでから、気づく。
まだ若い、女の相貌である。長い髪で顔の半分を覆っているのがもったいなく思えるほど、目鼻立ちのくっきりした美女だ。頭から爪先まで、闇に融 けるような黒い衣をまとい、雨を弾いている。
その格好でうつむいていたのが、急に顔を上げたので、白いかんばせだけ夜闇に浮かんだように見えたのだった。
隣にはもうひとり、同じ風体の、やや小柄な連れがいた。弟か、妹だろうか。こちらは、じっとうつむいたまま、激しい雨に耐えている。 -

イルーシャ
夜分にすみません。我々は、旅の者です。もしよろしければ、お泊めいただけませんでしょうか? もちろん、お礼はいたします……
-
長いまつ毛を揺らし、楚々として
希 う姿は、こんな高嶺の花めいた美女にそんなことをさせている、という倒錯的な快感を呼び起こしてやまなかった。 -

ジース
(田舎者にゃ、目に毒だよ)
-
脳裏に浮かぶ、眉をひそめた妻の幻影に言い訳をしてから、ジースはうなずいた。
-

ジース
礼なんていいさ。早く入りな、おふたりさん。雨で身体が冷えてるだろう。
-

イルーシャ
まあ、なんてお優しいこと。恐れ入りますわ。
-
ほれぼれするような美声の持ち主が、田舎者には縁遠いていねいな口調で礼をいうものだから、面映ゆくて仕方がない。ジースは、そそくさと引っ込んで、ふたりを招き入れた。
-

ジース
大変だったろう。このへんじゃ連日、長雨が続いててなぁ。
外套 は、暖炉の脇にでも置いて乾かしな。見てのとおり床は地面だから、遠慮しないで濡らしちまっていい。 -

イルーシャ
ご親切に。
-
ふたりは、ばさりと黒い外套を脱ぎ、手にしていた武器を地面に置いた。そんなものを持っていたのか、と視線をやって、ジースはぎょっとなった。ふたりの武器が、巨大な筒と鋭い鎌という、空恐ろしい代物だったからというだけでなく――それらが、ぎょろりと目を動かして、こちらを見たからだった。
-

ジース
か、〝顔あり〟か。
-
呪装符を喰らい、力に換える、特殊な呪具。その扱いは難しく、容易に与えられることもない。これを手にしているということは、氏族でも有数の戦士という証だ。
-

イルーシャ
〈死焔族〉のイルーシャと申します。
-
女が、にっこりと微笑んだ。包み込むようなやわらかさを感じさせる、穏やかな微笑だ。ぴしりと整いすぎているあまり、冬の雪原のような冷たい印象を与えかねない顔立ちが、春の訪れを思わせるものへと変わるほどだった。
-

ファルク
弟のファルクです。どうも。
-
もうひとりは、小柄な少年だった。姉とよく似た彫りの深い顔立ちを、やはり髪で半ば覆っている。
姉と違って、にこりともしない。どこで誰が死のうと知ったことかと北風を吹かせる、冬そのものの面差しだ。
なんとも対照的なふたりだと思いながら、ジースは告げられた氏族の名を反芻 した。 -

ジース
〈死焔族〉……。
-

イルーシャ
我々は〈死界の焔〉をトーテムとする氏族。嘆きのあまり地上に呪縛された死者を黄泉路にいざなうのが使命ですのよ。
-

ジース
はあ……そりゃ、大層なこったなぁ。
-

ファルク
そうでもねーですよ。迷える死者なんて、どこにでもいるもんです。
-
ファルクが、丁寧なのかぞんざいなのかよくわからない口調で言って、視線を向けてくる。
-

ファルク
たとえば――
あんたの奥さんとかね 。 -
ぎくりと、ジースは身をこわばらせた。
動けない。気圧されて。鋭く冷たく浴びせかけられる少年の視線が、そのまま死線と化している。首筋にナイフをあてがわれたように、眼差しだけで身動きを封じられる―― -

ファルク
旅人が――消えるってね。噂になってんですよ。西の街に行こうとして、この村を通った連中ばかりがね。いつまで経っても着かないって。
-
いきなり何を、とジースは言おうとしたが、声が出なかった。まぎれもない本物の殺意を、ファルクの瞳に見たからだった。ジースの命を断つことなど毛ほどもためらうことはないだろう、ということが、なぜかはっきりわかった。同じような瞳を見たことがある――どこで? 誰かに殺意を向けられることなどなかったはずなのに――
-

ファルク
いるんでしょ――ここに。
-
ファルクは、天井に視線をやった。雨漏りのひどい天井。ぴちゃん、ぴちゃんとものさびしい音を奏で続けている――
-

ファルク
旅人を喰らう怨霊が!
-
少年が、鋭く断じた瞬間。
天井から落ちる雨垂れが、血の色をした刃となって、彼の頭上に降り落ちた。