 LOADING
LOADING LOADING
LOADING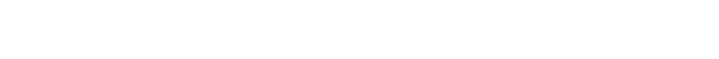

この「AFTER STORY」は「DARK RAGNAROK 黒の後継者」の後日談となっております。
戦いは終わった。
帝国、連邦、タイカン。
3つの国の連合軍とあたしたち後継者が、闇と戦うために波蝕の島に集まった。
その戦いで、あたしは決して取り戻すことのできない過ちを犯した。
「……リーラン」
連合軍の船舶が停泊する港。
その場所にタイカン軍の副官である彼女がいた。
「……セレナ」
リーランが振り返る。
戦いが終わり、連合軍が自分の国へ帰る準備を始めていた。その間、リーランとは一度も話すことができなかった。
一度なら偶然かもしれない。けれど二度、三度と続くうちに偶然じゃないと確信した。
リーランに避けられているのだ。
「……何をしに来たのですか?」
リーランの声音は固い。
とても冷たく、鋭く険しい視線でこっちを睨んでいる。
心臓が凍りつきそうになる。
でも、黙りこくるわけにはいかない。そんな資格はないのだ。
だって、どれだけ謝っても足りないことをしたのは、あたしだ。
「……ごめんなさい」
あたしは謝った。
声を震わせないように。
「許してもらえるなんて、思わないわ……。でも、ケンセイに誓ったから……。あたしにできることがあるなら、何でもする。本当に、ごめんなさい……」
そう言って頭を下げた。
このままリーランが波蝕の島を離れたら、二度と会うことはできない気がした。
拒絶されたまま離れたら、取り返しがつかない気がしたのだ。
「許すわけ、ないでしょう……」
はっと、あたしは顔をあげた。
リーランは仇を目の前にしたような顔で、拳を握りしめている。
「あなたのせいで、ケンセイ様は死んだんです! あなたのせいで!!」
リーランが怒気をみなぎらせて近づいてくる。
あたしは固まって、息をのみ、立ち尽くすしかなかった。
「何でもするなら返してよ……! ケンセイ様を返せ!!」
リーランの目に涙があふれ、目の前で膝から崩れ落ちた。
そのままあたしの服を掴み、あたしを叩く。
「リーラン、あたし――」
「許されると思わないでください……」
息を飲む。
リーランが鬼気迫る形相でこちらを睨む。
途端に世界が真っ暗になり、何もない世界で、リーランの声だけが響く。
「セレナ。あなたが死ねばよかったのに……」
「うわぁあああああ!!!」
あたしは叫び声を上げて、飛び起きた。
体中に冷や汗をかき、肩で息をしていた。
思考が追いつかない。何が起きたのか、さっぱりわからなかった。
「はぁはぁはぁ……」
ぐるりと周囲を見回す。
綿を詰めたベッド、簡素な机、陽の光が差し込む窓。
あたしは波蝕の島にある、自分の部屋にいた。
「……夢……?」
夢だ。
今のは現実ではなく、夢だった。
それがわかって心の底から安堵する。
だが現実が夢よりもマシだということはないのだ。
なぜなら――
戦いが終わった後、リーランが一度もあたしと顔を合わせてくれていないのは、事実なのだから。
あたしは臆病者だ。
だから勇気が欲しかった。覚悟が、欲しかった。
リーランと会わないといけない。そう思っていたら自然と足がこの場所に向いていた。
波蝕の島でも、海を望むことのできる高台だ。
潮風は冷たかった。雲ひとつない、突き刺すような青空だ。
ここで、ケンセイに言われた。
『戦争が始まったら、お前は前線に立つな。予備隊として後方に控えろ』
もしあの時、言うことを聞いていたら――
今さら後悔しても、遅い。
遅いのだ。
どんなに後悔したところで、ケンセイは戻ってこない。
戦いが終わった後、あたしは前へと進まなくちゃいけないと、強く思った。
そのつもりだった。
でもリーランが会ってくれないことで、もう、恐怖と不安に取り囲まれている。
波蝕の島にいる兵士みんなの視線が、お前は必要のない人間だと言っているように見える。
誰もがみんな、あたしがどんなに最低なヤツなのか、話しているように見える。
辛い。怖い。逃げたい。
息を飲む。世界のすべてがあたしを憎んでいるような気がした。
視界がぼやける。
あたしは口を引き結ぶ。
拳をぎゅっとにぎる。
「泣くな……甘ったれるな……!」
泣いちゃいけない。泣けばすむ問題じゃない。
それじゃ、何も変わらない。
「ここにいたか」
幼いのにどこか達観した響きの声。ネロの声だ。
なんで、こんなタイミングでやって来るのだろう。
「なに? なんか用?」
声が震えて、うわずっていた。
最悪だ。こんな姿を見せたらいけないのに。
だから強い口調で、どうってことない風に返事をしようとする。
その姿がどうしようもなく惨めで滑稽だと思ったが、他にどうすればいいのか、わからなかった。
「なんだその口の利き方は」
「ひとりにしてくんない? ちょっと考え事してんの」
我ながら、なんて言い草だ。
どうしてあたしはこんな言い方をするんだ。
でもそうやって強がる以外に、弱い自分を隠す方法を知らないのだ。
アマリアに託されて、ケンセイを犠牲にして、ネロに期待されて……
そんな奴がただの臆病者だって思われるのは、嫌だから。
「リーランのことか」
あたしは、はっとネロを見た。ネロは見透かすような目でこちらを見ていた。
「なによ、急に……」
「あれから一度も顔を合わせていないようだな。リーランを避けているのか、貴様は」
「ち、違うよ! あたしじゃなくて、リーランが……」
ネロはじっとこちらを見ていた。
あたしは口をつぐむ。
ネロは知っているのだ。あたしがここにいる理由も。何を考えているかも。
それがわかった途端、ネロの顔を見られなくなる。
恥ずかしい。
消えて、なくなりたい。
「まさかリーランならば手放しで応援でもしてくれると思ったか? 甘えるなよ、セレナ。貴様は恨まれても仕方がない」
「……そんなの、わかってる」
「だったら貴様はここで何をしている。恐怖し、逃げているんじゃないのか」
「――っ! ちがう! あたしは……」
『何も出来ず死ぬことが怖い。いいんだよ、それで。俺だって怖いさ』
言葉に詰まった瞬間、ケンセイの背中が脳裏をよぎった。
どんな絶望的な状況でも決して動じない、覇王の姿。
『期待に応えられるかわからない――』
『でけえこと言ったら怖くて当たり前なんだよ。だがそれでも自分で決めた道を突き進む。道がねえなら切り開く。……恐怖も不安も振り払うなら、前に進むしかねえんだ』
ケンセイはあたしにそう言った。
その言葉はまっすぐで、ひねりのない、そのままの、真実だ。
「あたしは……」
それでも怖い。
リーランと向き合うことが。
「貴様は何を目指す、セレナ。どのような道を歩むつもりだ? お前が何かを決意し、選んだのならば、こんなところで立ち止まっている暇はないはずだ」
もう嫌だ。
あたしの弱さのせいで、誰かを犠牲にすることも。
どうしようもない悪意のせいで、誰かが苦しむ姿を見ることも。
「あたしは……世界を平和にしたい。闇を司る悪を討ち倒したい……。だから――」
わかっている。途方もないおとぎ話みたいな理想だ。
そんなものに手が届くなんて、誰も信じてはくれないだろう。
そもそも、そんな言葉を期待されているわけじゃない。
だって、あたしはケンセイじゃない。
あたしは、あたしの道を進まなければならない。
あたしはゆっくりと伏せていた目を上げる。
怖くてもネロの瞳を見つめる。
「守りたいんだ。目に映るものを……。手の届くもの全部の……力になりたい」
そう言うとネロは視線を外して、浜辺のほうを見下ろした。
連合軍の船舶が停泊しているあたりだ。
「……タイカン軍は今日中には出立するそうだ」
ネロの声に背中を叩かれたような気がした。
「ここにいていいのか、セレナ」
いいわけ、ない。
あたしはネロに礼を言って、走り出した。
港には三つの軍の船が停泊している。
帝国、連邦、タイカンだ。
帝国と連邦の両軍はまだ上船の準備すら始めていない。
しかしタイカン軍は、すでに出港のための一通りの準備が完了している。
これでは一刻も早くこの島を離れようとしているように見えても、仕方ない。
私はタイカン兵たちの姿を見渡す。
傷ついた兵士たちの足取りは重い。だがそれは自分の身が傷ついたからではないだろう。
乱世の島タイカンは統一された。
だが統一したばかりの島は、王を失ったのである。
「……どうしてくれるんです、ケンセイ様」
タイカン軍の副官である私は、誰にも聞こえないように呟く。
正直に言えば、まだあの人を失った実感は湧かない。
膨大な戦後処理に、指揮系統の再編成、そしてタイカンへの帰国の準備。
いくらこなしても無限に湧いてくるのではないかという仕事の量に忙殺されていた。
そのせいなのか、そのおかげなのか分からないが、私はぞっとするくらい平常運転なのだ。
だから、ふと考えてしまう。
ケンセイ様は実は生きていて、いつものように私に仕事を押し付けているだけなのではないか、と。
そして諸々が片付いたころ、帰るぞリーラン、と顔を出すのではないか、と。
そう、思ってしまうのだ。
要するに私はまだ、ケンセイ様の死を受け止めきれてはいない。
きっとじわじわと体を蝕む毒のように、私は喪失を実感することになるのだろう。
その未来を想像するのは、たまらなく恐ろしかった。
「いけませんね……」
頭をふって、余計な考えを追い出す。
兵士たちが上船を始めている。これから帰国の船旅だ。
私が下を向くわけにはいかない。覇王の兵であることを誇りとした皆の前で、折れるわけにはいかないのだ。
「負傷者から優先するように。私は最後に」
上船していく兵たちに声をかけていると、数名の兵たちが、私のもとに歩いてきた。
ライゴウ建国時から、ケンセイ様の近くに仕えてきた古株の兵たちだ。
「リーラン様、少々よろしいでしょうか?」
「どうしたんですか?」
「……戦の後、リーラン様はセレナ殿とは一度も会話をされていないご様子。その真意を、お聞きしたく思います」
兵の目は静かな闘志をたたえていた。
まるで死地の戦場に赴くような覚悟さえ感じる。
だからこそ、慎重に答えなくてはならないと思った。
「なぜ、そのようなことを聞くのですか」
「……ケンセイ様を死に追いやったのは、あの後継者です。もし、リーラン様が望まれるのであれば、我らが……」
兵たちは本気だ。
もし私がセレナを憎いと言えば、彼らはこれから波蝕の島で後継者たちを相手に戦いを仕掛けることを辞さないのだろう。
たとえまだ島にいる帝国、連邦の軍隊ごと敵に回しても、だ。
たしかに私は、ずっとセレナを避けてきた。
彼女が何度も面会に来るたびに、私は何かと理由をつけてセレナと会うことを拒絶した。
私はわからなかった。
セレナとどういう風に向き合えばいいのか。
彼女と向き合うことは、ケンセイ様の死を認めることになる気がしたから。
仕事で忙殺されていた、なんて言い訳だ。
本当は逃げているのだ。
けれども私のせいで兵たちが思い詰めてしまったのならば、その責任は私にある。
こんな時、ケンセイ様ならどうするのだろう。
そう考えた時、私はふと、ケンセイ様との会話を思い出した。
タイカンを統一し、波蝕の島へと向かう準備を進めている最中――
私は突然、ケンセイ様に休暇を取るように命じられた。
戸惑いながらも休みをとり、飛行島の方々と一緒に休暇を過ごした私は、タイカンの王宮へと帰ってきたのだった。
そして帰ってきたら帰ってきたでジャッキーやハオと一緒に軍編成に取りかかり、王宮につく頃には……
「すっかり日が暮れてしまいましたね」
王宮から望む城下町は、夜が深まるほど賑わいを増していた。
これからタイカンは平和になると連日お祭り騒ぎである。
私は灯籠の明かりをたよりに、王の間へ向かった。
ケンセイ様はこの時間、玉座で遠くを見つめていることが多い。
いっつも人を振り回すくせに、ちゃんと考えることは考えているのだからタチが悪いと思うのは私だけなのだろうか。
王の熟考を邪魔するのは気が引けたが、一応、休暇のお礼だけは口にしておこうと思い、ケンセイ様のもとに顔を出す。
「ケンセイ様、遅くなりすみません。休暇、ありがとうございました」
「休めたか」
「はい、おかげさまで」
ケンセイ様が立ち上がる。そして街を一望できる窓辺に近づいていった。
「来い、リーラン」
「は、はい」
どうしたのだろうか。
私は呼ばれるがままにケンセイ様のとなりに並び立ち、城下町を一望した。
「わぁ……」
戦場以外でとなりに立つことは、ほとんどない。
少しだけどぎまぎしたが、宝石箱を転がしたような街明かりがあまりにも美しくて、すぐに忘れてしまう。
「いい景色だよな」
「……はい、とても」
「波蝕の島での戦いが終わったら、国を建て直す。この景色を俺たちの手で守る」
「……はい!」
「タイカンの泰平が盤石なものになった後、俺はこの世界から争いをなくすつもりだ。世界を平和にするために、世界をとるぞ」
またしても呆気にとられる。
いつも想像の上をいく発想をする人だと思っていたが、まさかそんなことを考えていたとは。
「それとついでだが、戦いが終わったらセレナをタイカンに連れてくるつもりだ。あの馬鹿を鍛え直してやる」
横顔を見上げる。
とても楽しそうな表情に私はぽかんとしてしまった。
「驚いたか?」
「それはまぁ……。しかし、どうしてセレナを?」
「……あいつが底抜けの大馬鹿だからだ」
「大馬鹿、ですか?」
ケンセイ様が肩をゆらして笑う。
「世界を平和にする。そんな理想を語り、本気で信じる奴はただの馬鹿だ。本気でそれを口にして、本気でその理想に挑む奴が、果たしてこの世界で何人いると思う?」
「私のとなりにいますけどね」
「……ふん。だが俺もタイカンを統一するまで、何度も失敗したさ。邪魔もされた。それでも、タイカンをひとつに統一し、平和な国とする夢を見てきた。理屈じゃねえ。合理的な理論なんざ、そこにはねえ。あるのは、理想を果たすための、覚悟と意志だ」
「ケンセイ様……」
「まともじゃねえのさ。根っからの馬鹿じゃなきゃ、そんな道を進むことはできねえんだよ」
「……だから、セレナを鍛えると?」
「初めてセレナがタイカンに来た時、あいつは言った。闇の王を倒すってな」
「……ああ、そんなこともありましたね」
「あいつは本気で言ってるんだ。己の実力が足りないことなど百も承知。それでも、自分の身の丈に合わぬ理想に手を伸ばそうと、必死にあがいてるのさ」
ケンセイ様は笑う。そして馬鹿なやつだ、と呟いた。
少しだけ寂しかったが、仕方ないとも思う。
確かに私は、世界の平和を、という風には考えない。
タイカンの平和。
それだけで十分。ずっと戦乱の世に生きてきた身からすれば、ありえないほどの奇跡なのだ。
今以上を望むなんて考えたこともなかった。
「だからリーラン」
「はい?」
セレナとケンセイ様がともに並び立つ姿を想像して、なぜか少ししんみりしてしまった。
そんな私にケンセイ様は命令する。
「これからも俺を支えろ。俺が迷いを断ち切り、前を向いていられるのはお前がいるからだ」
「……はい?」
「お前は俺に尽くせ」
さらっととんでもないことを命令してくる。
言うに事欠いてこの人は、世界を平和にするまで私をこき使うつもりでいるのだ。
「任せたぞ、リーラン」
少しは私の意見を聞いてください。
そんなことを思ったが、なぜか、今日だけは許せてしまう気がした。
「お任せください。リーランが、王の進む道をお支えします」
セレナへ怒りを向ける兵士たちが、ケンセイ様の仇討ちをすると私に訴えかける。
私がセレナを避けていることを、彼女に怒りを感じていると思ったのだ。
「たしかにセレナを庇い、ケンセイ様は倒れました」
「ならばリーラン様!」
兵たちはいさみ、憤怒のまま今にも動き出しそうだ。
だから包み隠さず、本心を話すことにした。
「……私も、思いました。セレナがいなければ、ケンセイ様は死ななかったのではと……。ですが――」
私の心にあったのは、それだけではなかった。
「ケンセイ様はご自分の意志でセレナを守りました。そして、託されたセレナは立ち上がり、務めを果たしたのです」
ケンセイ様はあの子を守った。
きっと何度だって、あの人は同じことをする。
私はケンセイ様に任された。
だから私が最初に受け入れなくてはいけなかったのだ。
ケンセイ様は、もういないということを。
「私はセレナを許します。そしてケンセイ様が信じたあの子を、私も信じる――」
ケンセイ様がいないことを前提に話すのは、辛い。
微笑んで見せるつもりだったのに、頬を涙が伝った。
「余計な心配をさせてしまい申し訳ありません。私はセレナのことを憎んでいません。そしてあなた達にも、そんな風に思ってほしくない。なぜならケンセイ様がそんなこと、望むわけないですから」
思っていることをそのまま伝える。
それが今できる精一杯のことだ。
「……承知いたしました。リーラン様」
伝わったのかどうかはわからない。きっと心から納得などできはしないだろう。
けれど兵たちは引き下がってくれた。
私はそのことに深く感謝した。
「さぁ、あなたたちも上船を」
その時だった。
「リーラン!」
ふりかえる。
そこには、大きく肩で息をしているセレナがいた。
あたしは走った。
肺が痛い。呼吸をするのがもどかしくなる。
だけど伝えなくてはいけないから、とにかく走った。
そして浜辺までたどり着き、今まさに船に乗り込もうとしている彼女の姿が見えて、叫んだ。
「リーラン!」
リーランが振り向く。
とても驚いた顔をしている。
「……セレナ」
「よかった……やっと……会えた……」
あたしは息を整えながら彼女に近づく。
リーランの背後にはタイカン兵のみんながいた。
その視線が恐ろしかった。
でも受け止めて、リーランの前に立つ。
リーランは泣いていた。
彼女の頬を伝う涙を見ると、胸が痛い。
けれどあたしが今リーランにするべきは、口先だけの謝罪ではないのだ。
「あたしは、力になりたい……」
リーランから目を逸らさずに、続ける。
「助けを求めている人の力に……困っている人の力に……あたしができる、ぜんぶのために……!」
拳を握る。
愚かだって言われるに決まってる。
お前なんかには無理だと言われるに決まっている。
それでもあたしは――
「この世界のために、力になりたい……なにより、リーランの力になりたい……!」
もう逃げない。
どんなに怖くたって立ち向かう。
あたしにはそうする義務があるのだ。
リーランが静かに目を閉じる。
続く言葉がどんなものであろうと、あたしは覚悟を決める。
「……タイカンはこれからが正念場です。国はひとつになったばかりなのに、ケンセイ様がいないのです。またバラバラになるかもしれません。最悪、再び戦乱の世に戻ってしまうかもしれない」
リーランが目を開く。そして微笑んで、あたしを見る。
「力を貸してください、セレナ」
「……うん。……うん!」
その微笑みを見た途端、視界がにじむ。
「……うん。力に、なる……! ぜったい……!」
涙をおさえようとしても、止まらず溢れてくる。
なんてかっこ悪いのだろう。
あたしはまた泣いていた。
「ホント、すぐ泣きますね、セレナは」
リーランは呆れたように嘆息する。
そしてやれやれとあたしの涙を拭う。
「だっで……リーランが……ずっど、無視、ずる、からぁ……」
嗚咽がもれて、まともに喋れない。
だがずっと気になっていたことだった。
リーランにずっと避けられていると思った。
それなのに、急に微笑んで、正直、何がなんだかわからない。
「……ごめんなさい。たしかに私は、あなたのことを避けていました。あなたと会うことが、ケンセイ様がいないことを認めるようで、怖かったのです」
「ううん……いいよ、ぞんなの……いい……! ありがどう……リーラン……!」
「でも決めました。もう、私は逃げません。ケンセイ様が歩んだ道を、そのまま歩いていきたいと思います。できれば、あなたと一緒に」
リーランがあたしに手を差し出す。
その手は握手を求めているように見えた。
「ひっく……リーラン……」
「それにしても……」
「な、なに……?」
「あなたのメンタルは杏仁豆腐よりもやわらかいです。とんでもなく甘ちゃんです。私の知る限り、あなたよりも軟弱な人はいませんよ。ふふふ」
「ひ、びどい、よぉ……!」
「ケンセイ様には及びませんが、その一挙手一投足を見てきました。ケンセイ様ならあなたのへっぽこ具合をどう叩き直そうとするのか、想像がつきます」
「へっぽこ……」
「私と一緒に、ケンセイ様が進んできた道の先を歩いてください。その代わり、あなたが前に進むためのお手伝いをいたします」
きょとんとするあたしに構わず、リーランは続ける。
「落ち着いたら、タイカンに招待します。必ず来てくださいね」
まだ、目の前にはリーランの手が差し出されている。
「それともやっぱり、甘ちゃんへっぽこセレナには無理でしょうか……」
あたしは首をふる。
涙を拭い、リーランの手を強く握り返す。
そして、自分で選んだ道を進んでいく覚悟を言葉にするため、口を開いた。